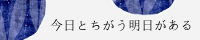2. 仕事ができて、帰国子女で、いい男
「愛ちゃん。ヘルプミー!」
愛が通常通りの業務に励んでいるところ焦った声がフロアーに響いた。
パソコン入力に集中していた愛が顔を上げると、芳村部長と積み上げられた段ボールが見てとれた。
デスク二つ分のどこからそんな荷物が出てきたのか不思議に思いながら、部長部屋に運んで片づけるのにはそこそこの時間がかかることを想像する。
「引っ越しのお手伝いですね?」
「うーん。手伝って欲しいのはやまやまなんだけど、自分でやらないとさ、あとあと収拾がつかないだろうから、がんばるよ!」
「ああ。はい。……それで、『ヘルプミー』って」
「そうそう。それそれ。……悪いけど、空港まで高坂を迎えに行ってほしいんだ」
芳村部長は、両の掌を合わせてお願いポーズを取っている。
「……はい。承知しました」
しょうがないから迎えに行きましょう、と心の中でごちて愛はパソコンの入力画面を閉じた。
高坂 理久とは面識がなかった。どんな人物なのか愛は知らない。愛が入社した当時はアメリカ駐在だったと思う。
のちに中国駐在になって、数か月に一度のペースで日本に戻り、ここ本社の海外事業部に出張していたようだが、愛には関わりがなかった。
「あの。高坂課長は、どんな方ですか?」
「そうだな。仕事ができて、帰国子女で、いい男だよ」
帰国子女と聞かないまでも、アメリカ、中国で働いているくらいだから外国語は堪能なのだろう。
けれど、いい男というのは、抽象的すぎる。
「容姿を具体的に教えてください」
「なに、高坂のこと、興味があるの?」
「……いえ。空港でわからないと困るので、どんな人なのか知りたいだけです」
「ああ。びっくりした。そういうこと」
うんうん、と芳村部長は頷いた。
「そうだな。イケメンだな。隙のなさそうというか、神経質そうな印象かな。営業に1年くらいは居たらしいんだけど、そのころ俺は企画に居たし、直接会ったことはないんだよな」
「え。空港に迎えに行くって、……それだけの情報で行くつもりだったんですか?」
「まあ。そうだけど。一応、社内誌の写真は確認したよ。新入社員のプロフィールが毎年4月発行のに載ってるだろ? あれを見た」
入社の時の8年も前の写真。面影があるのだろうか。
「えっと、その社内誌、見せてもらえます?」
「あー。どこにいっちゃったかな?」
積み上げられた段ボールを指差し、芳村部長は眉を下げた。
この状況だ。そう簡単には見つけられそうもない、と納得するしかない。
「……わかりました。空港まで行ってきます」
「悪いな。よろしくー!」
芳村部長は、スラックスのポケットから車の鍵を取り出すと、愛の手のひらに預けた。
愛としては会社の地下駐車場に自分の車があるので芳村部長の車は必要ないが、断らずに営業部フロアーから出ることにした。
「愛ちゃん。聞いてたよ。高坂さんを迎えに行くんだって? いいな〜」
同期の中沢 美鈴が座っている椅子を回転させ愛の顔を覗き込んできた。
チャーミングで愛らしいその表情は営業部のマスコット的存在な上、顔が広いので情報通でもある。
「そんないいものじゃないって。美鈴ちゃんに代わってほしいくらいだもん。あ。高坂さんって知ってる?」
「知ってるも何も、超有名人だよ。知らない人の方が貴重だと思うよ」
愛の方を見て揶揄う仕草をした。
「……そうなの?」
「うん。あー。愛ちゃんは興味のないことはさっぱりだからね。高坂さんが帰国した時なんか社内が騒然としてる。社食が混み合って席取り合戦なんだから」
「ふーん。そうなの」
愛はお弁当を持ってきているので混む時間の社員食堂は利用せず、社食の隣にあるカフェテリアで食べている。そして食後にはコーヒーを飲むのが日課だ。
「それで、具体的にはどんな人なの?」
「高坂 理久。30歳。入社当初は営業部配属。難関国立大卒のエリート。超のつくイケメン。背は180センチ超。短髪黒髪。清潔感があって、シャキッと背筋が伸びててスーツの着こなしもスマートなの。人当たりもいいし、悪いところを探そうと思ってもないんだよね。彼女、いるのかな〜?」
「……」
美鈴のトロンとした顔を見ながら、そんな完璧な人がいるんだ、と愛は心の中で苦手意識を持った。頭の中ではサイボーグのイメージがぼやっと浮かんでいた。
空港にて。
愛は飛行機が到着したことを確認したものの、一向にそれらしき姿を見つけられない。
もしかしてすれ違ってしまったのだろうか。
愛はロビーで待ちぼうけ。途方に暮れて泣きそうになっていた。
もう機内から人が出てくる気配もなくなり、入国カウンターで問い合わせようかと、愛は視線をさ迷わせた。
「高坂 理久、だったよね」と名前を復唱して愛は一歩踏み出した。
その時、グッと愛の腕を引っ張る小さな手があった。
未就学児らしい子どもが愛を真っすぐに見上げている。
「ぼく、どうしたの?」
愛は子どもの背の高さに合わせるように腰を落として尋ねた。
「理久くん、お熱出したの」
「リクくん?」
子どもの指先を見ると、ソファーに身を投げ出した大きな体の人が熱とりシートをおでこに張ってマスク姿で目をつぶっていた。
ヨレヨレのグレーのパーカーと黒っぽいパンツ。ボサボサの頭はお世辞にもキチンとした人には見えなかった。
「いま、『タカサカ リク』って言ったよね? 理久くんのことを探してるのかと思って」
子どもは愛の顔を覗き込んだ。黒目が大きいな、と愛は見とれる。
「ぼくのママなの?」
え? ママ?
何か勘違いしている子どもに手を引っぱられながら、ソファーに近づいた。
「タカサカ リクだよ」
愛の右手を小さな手が包む。手を握り返して、呆然と愛が口を開けた。
「高坂課長、ですか?」
目を瞑っている人が、うっすらと目を開けるとマスク越しにもわかるくらい熱っぽい吐息を吐いた。
相当熱が高そうだな、と思いながら愛は「高坂課長ですよね」ともう一度呼びかけた。
ただ物憂げに目をしばたたかせただけで声を発することはなかった。
愛はそばに立つ子どもと、物言わない人の間を繰り返し見てどうするべきか悩み、一本の電話をかけた。
結局、「忙しいんだけど」と迷惑そうな友人の旦那さんの病院に押し付けて、愛は子どもを連れて会社にある自宅に帰った。
芳村部長には高坂課長について報告したものの、子どものことは切り出せなかった。タイムロスを若干変に思われたかもしれないがしょうがない。
遅いお昼を子どもといっしょにとってから営業部に戻ると、芳村部長は相変わらず段ボールと格闘しており、気づいた様子もなかった。
「お疲れさん。高坂のことありがとな。病院も連れてってもらったんだって?」
「はい。かなり熱が高くて、病院で診てもらいました」
「ほんと。悪かったよ。ま。明日明後日とゆっくりと休めば良くなるだろ」
芳村部長の楽観的な見方に愛は頷くしかなくデスクに戻った。
それから溜めていた仕事を一気に片付けると定時に切り上げて、美鈴の物言いたげな顔を笑顔で無視し、自宅へ足早に戻った。
(2017/3/11)
イラストもずねこ様