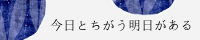12. わたし好きな人ができたの
畑の家に着く頃にはすっかり日が暮れて、小さな平屋の家は夜空に溶け込んでいた。
遮光カーテンが引かれた縁側の腰窓からは、うっすらと温かそうな灯りが漏れていた。
正広が来ている。
愛は運転してきたSUV車を駐車すると、ハンドルにかぶさり思いに沈む。
一時間ほど前の優花との会話を思い出し途方に暮れていた。
今夜こそは正広に言わなければいけない。
あやふやな男女の関係を終わりにさせないと。
どんな言葉を選べば正解なのだろう。
恋人でもないふたりには、明確な始まりがあった訳ではない。
だから当然、別れの言葉は似合わないだろう。
それに、今まで一度も気持ちを確かめ合うこともなかった。
答えが見つからなくて、愛は暫く車から出ることができなかった。
重い腰を上げ車から降りたものの心は決まらないままだ。
そろそろと元気なく引き戸を開け、明るい声を作って「ただいま」と呼びかけた。
玄関のたたきには男物のスニーカーが揃えられている。
静かで物音がなかったので愛は首を傾げた。
いつもなら正広が台所から出てきて「おかえり」と迎えてくれるのに。
聞こえなかったのだろうか。
愛はパンプスを脱いで上がると台所は明るく、廊下と台所を繋ぐガラス扉も開いていた。
ひょいと覗いたが正広はいない。
卓上には今晩のおかずが置かれ、お茶碗と箸が二揃え、愛と正広の分がいつも座る辺りに用意されていた。
鰹だしと味噌の香りが食欲をそそる。
その匂いの元、台所の奥にあるガスコンロには、味噌汁の鍋もあった。
ここに正広がいないとなると、二間続きの和室にいるのだろう。
「ただいま」
声を掛けてからふすまを開けると、布団の上に正広はいた。
目を閉じている。
仕事柄、朝が早い正広のことだから、疲れて眠ってしまったのだろう。
愛は音を立てないように畳を歩き布団のそばで膝を付くと、正広はゆっくりと目を開けた。
ふたりの視線は交わったまま。
お互いが動き出すまで、愛は自分がどんな表情をしているのか、正広が何を思っているのか、時間が止まっているように感じた。
その間を、気まずいと思うのは愛だけだろうか。
「愛。……おかえり」
布団の上に上半身を起こした正広は表情のない顔をしており、起き抜けの声は掠れ低かった。男らしい無骨な手のひらが愛の頬をするりと撫ぜた。
「……」
正広に引き寄せられ抱きしめられると愛は身じろぐこともできなかった。
耳元では穏やかな呼吸音。
言葉もなく包まれて愛は目を閉じた。
会えば身体を繋げてきた。
数えきれないくらい何度も。
学生の頃。
異性だからという少しの好奇心と、幼馴染という気安さから一線を越えてしまった。
悪いことをしているつもりはなかったが、優花の想いを知った以上、このままではいられない。
その答えだけが愛の中で育ち大きく膨らんでいた。
優花のためだけではない。
愛と正広のためだ。
けれど、お互いを手放すことはできるのだろうか。
身体に馴染んでしまった行為に未練はないのだろうか。
「お布団、干してくれたんだね」
「ああ。天気よかったから。……取り込んだ布団から日向の匂いがして気持ちいいな、って寝ころんだあたりから記憶がない。いつの間に寝てたんだろ」
正広は自嘲気味に呟くと、愛の額に唇を当ててから立ち上がった。
「正広が寝ちゃうなんて、疲れてる? 仕事、忙しいの?」
肝心なことを言葉にできないもどかしさを感じながら愛は正広を見上げた。
「いんや。いつもと変わりない」
愛の腕をとって立たせると、手を引き台所へ連れて行かれる。
「お味噌汁の匂い。いい匂い」
ガスコンロへ歩いていくつもりが、正広の手で遮られた。
「いいよ。愛は座ってな。俺がするから」
「はぁい」と素直に返し愛は食卓に着く。
愛はいそいそと晩ごはんの準備をする広い背中をぼんやりと見つめた。
こうしてごはんの用意を自らかって出る正広は珍しくない。
一見、亭主関白っぽい風貌なのに、そうじゃないところが正広のいいところだ。
結婚したら本当にいい旦那さんになるにちがいない。
竹籠に入った新鮮な卵を、味噌汁の鍋にぽとりと割り入れる正広を見るのはもう何度も繰り返している。
この曖昧な関係を終わりにするなら、もうこんな風に見ることも、いっしょに食べることもなくなるかもしれない。
ごはんをよそって差し出された茶碗から、湯気が上っている。
出来立てほやほやの卵入りの味噌汁も完璧な仕上がりだ。
愛は言いしれない寂しい気持ちを「わぁ。美味しそう!」と誤魔化した。
きっと全部を手放さなければならないだろう。
身体の関係といっしょに無くしてしまうだろう、この温かな関係も終わりにしなければならない。
味噌汁に落とした絶妙な半熟加減の黄身に箸を入れ、愛は椀に口をつけた。
「ん〜。美味し〜! 正広の作る玉子のお味噌汁だけは真似できないんだよね」
「ふん。当然。毎日欠かさず作って食べてるんだから。慣れだよ、慣れ!」
もう一生口にはできないかもしれない玉子のお味噌汁を前に、別れの言葉を繰り出した。
「正広。……わたし、……わたし好きな人ができたの。……だからこうやってふたりで会うのをやめたい。彼のことを愛してるから、不誠実なことだけはしたくないの」
頭で考えていたことを一息で言ってしまってから、破れた黄身が味噌汁の中に広がっていくのを見つめた。
「はあ? 唐突に何を言い出すんだ。もう一回俺の目を見て言ってくれよ! 愛」
慌てて取り乱した声音が愛を脅かす。
ハッとして向かいに顔を上げると、切ない表情がまっすぐ愛を射ていた。
怒りではない、むしろ愛情さえ感じる深い色合いに愛は戸惑う。
「はぁ〜。突然だな。……いつか言われると思ってたよ。想像してた以上に遅かったけど。なんとなくこうなるってわかってた。俺、ヘタレだろ? 鶏といっしょに育ったもんだから、しょうがねーよ。愛はでっけー会社の社長の娘。お嬢様の愛とはずっと居られないってこともよくわかってたし。たださ、俺から手放してやることはできなかったってだけだから」
「正広はヘタレじゃない。それにお嬢様とか言われたくない。そんなんじゃない」
社長の娘とか関係ない。そんなことを言ったら、正広だって今勢いに乗った玉子焼きの会社の社長だ。
「ふん。どうだか。ヘタレじゃなかったら、とうに愛を俺のもんにしてただろうよ。う〜。冗談抜きできっついわ」
正広は箸をぽいっと手離すと、頭を抱えてしまった。
「……」
「あ〜あ。このまま成り行きで最後までいけると思ったのにな。笑えねえ。……で。愛の好きな人って誰だよ。……先週連れてきた男だろ。あの高坂ってやつだろ」
愛は驚いて目を見開いた。
別れの常套句を告げればいいと思っていたから、『好きな人ができた』と言ったまでだ。
まさか理久を巻き込むことになるとは予想もしていなかったが、愛は否定する上手い言い訳が浮かばなくて、思わず首を縦に振ってしまっていた。
ヘタレは、愛のほうだ。
愛はあまりにも動揺しすぎて、箸を銜えて固まっていた。
(2018/9/3)
イラストもずねこ様